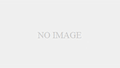秋の七草は、春の七草ほど、なじみがありません。
でも、秋の七草が選ばれたのは、奈良時代。平安時代からの春の七草より、古くから愛されてきました。
お月見には、ススキやハギ、キキョウなど、秋の七草をお供えしたいですね。
ここでは、「秋の七草」の意味と由来と花が見つかる場所と時期について、写真と特徴(漢方の原料など)、自生する場所など、覚え方とあわせてご紹介します。
1秋の七草の意味と由来
・秋の七草は、鑑賞するもの。
・奈良時代の歌人、山上憶良が選び、万葉集にのせられました。
1)意味
春の七草(七種)は、食べるもの。野菜が少ない冬に、栄養を補う意味がありました。
秋の七草は、野に咲く秋の花を見つけて、喜び愛でるもの。鑑賞用です。
2)由来
由来は、奈良時代の有名な歌人、山上憶良(やまのうえのおくら)の歌から。
秋の花として7つを選んで、和歌に詠みました。
秋の野に
咲きたる花を
指折り(およびをり)かき数ふれば
七種(ななくさ)の花
・・・秋の野原に咲いている花を、指折り数えてみたら、七種類の花がある。
萩の花 尾花 葛花 瞿麦(なでしこ)の花 姫部志(をみなへし)
また藤袴 朝貌の花
・・・はぎ、おばな(すすき)、くず、なでしこ、おみなえし、ふじばかま、あさがおの花(=ききょうの花)

指を「および」と読むのは、子どもを相手の言葉だから、ともいわれているそうです。ー奈良市「万葉歌碑巡り」
山上憶良は、貧しい人たちや、家族や子どもへの愛情を歌に詠んだ人です。
子どもに語りかけている形の歌なのかもしれませんね。
![]()
![]()
秋の七草の歌は、『万葉集』におさめられて貴族たちの共感をよび、現代まで、多くの人に愛されてきました。
今も、秋の野原(花野)に出て、短歌や俳句を詠む人たちがいます。
秋の七草の花の名前は、すべて、俳句の秋の季語になっています。
2秋の七草の種類、花が咲く時期と見つかる場所
1)秋の七草の種類・花の時期
暦の上での秋は、「立秋」から始まります。立秋は、旧暦でも、現代と同じ太陽暦の8月7日頃からです。*暦は、飛鳥時代に百済(朝鮮)から伝わりました。旧暦は太陰太陽暦です。
| 画像 | 和歌の漢字名 →現代の名前 | 花期(現代) |
 | 萩(はぎ) →はぎ | 7~9月 |
 | 尾花(おばな) →すすき | 9~10月 |
 | 葛花(くずはな) →くず | 8~9月 |
 | 瞿麦(なでしこ) →なでしこ | 6~9月 |
 | 姫部志(をみなへし) →おみなえし | 6~9月 |
 | 藤袴(ふじばかま) →ふじばかま | 8~9月 |
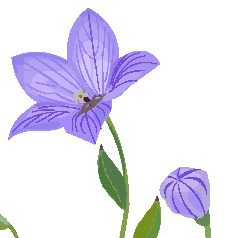 | 朝貌(あさがお) →あさがお :ききょう | 6~10月 |
朝貌(あさがお)は、ききょう
秋の七草の 「朝貌(あさがお)の花」は、朝顔ではなくて、桔梗(ききょう)だとされます。
朝顔や昼顔、木槿(むくげ)ではないかとする説もありますが、「日本の植物学の父」といわれる牧野富太郎(1862-1957)によると、どれもふさわしくないとのこと。
ききょうを朝顔とする平安時代の文献(『新撰字鏡』)も残っています。
・・・梅雨時から咲いていますが、花期は6月~10月まで。
2)咲いている場所、花の特徴
秋の七草は、野原の中にあって、きれいな花たちです。
秋の野の原っぱに、わんさか、またはひっそりと咲く秋の花たち。
どこに行くと見つかるでしょう。
萩(はぎ)


【花期】7~9月
【場所】原っぱ、道端
【特徴】マメ科で、小さな花をつけます。
道端や街路樹のそば、民家の庭でも見かけます。はっとするほど美しいですよ。
尾花(おばな:すすき)

【花期】9~10月
【場所】空き地、原っぱ、道端
【特徴】イネ科。茅(かや)とも呼ばれます。
葛(くず)

【花期】8~9月
【場所】空き地、原っぱ、道路端など。

【花の特徴】マメ科。花は大きく、濃いピンクから紫。ハギに比べるとちょっとどぎつい感じです…。
効能
根から、くず粉が作られ、葛まんじゅうや葛切りに。また、漢方の風邪薬「葛根湯(かっこんとう)」の原料にもなります。

瞿麦(なでしこ)
万葉集に詠まれた「なでしこ」は、カワラナデシコです。

【花期】6~9月
【場所】日当たりのいい草原、河原。
庭に植えられている以外では、自然の中で見かける機会は少ないです。自生が減っている地域もあり、埼玉では絶滅危惧Ⅱ類に分類されています。

【特徴】花びらはピンクや白で、先が細い糸のように分かれています。やさしく繊細な花で、「やまとなでしこ」とも呼ばれます。
効能
乾燥した種子は、瞿麦子(くばくし)と呼ばれ、消炎利尿や通経薬として使われます。
姫部志(をみなへし)
おみなえしは、平安時代に入って(古今集の頃から)「女郎花」と書かれるようになりました。都立薬用植物園
女郎は、もともとは「女性」という意味です。おみなえしの仲間には、花が白くて、全体にたくましい男郎花(おとこえし)という植物があります。

【花期】6~9月
【場所】日当たりのいい草原。自生が減っている地域もあります。

【特徴】小さく黄色い花が、まとまって咲きます。
効能
根は、漢方で、鎮静・消炎・利尿などに使われます。
藤袴(ふじばかま)
花の色が、藤に似ていること、花弁の形が袴(はかま)に似ていることからつけられた名前です。
↓藤色のはかま。横向き。


【花期】8~9月
【場所】河原など。民家の庭で見かけますが、自生は減って、環境省のレッドリストでは、準絶滅危惧とされています。

【特徴】キク科。細い糸のような花びらが開いて、房のようになります。咲き切る前、開き始めがきれいです。


効能
利尿薬や糖尿病予防などに使用されます。
朝貌(あさがお:ききょう)

【花期】6~10月
【場所】花屋では見かけますが、自生は減っています。環境省レッドリストで、絶滅危惧Ⅱ類にあげられています。
【特徴】梅雨時から、秋まで咲きます。
効能
桔梗根は、去痰薬として使われます。
*効能は、大阪薬科大学薬用植物園お花紹介を参照。
3秋の七草の覚え方
万葉集のまま、大体覚える
和歌は、五・七・五、七・七と、人間がとても覚えやすいリズムを持っています。
そのまま、指を折りながら十回くらい口ずさんで、だいたい覚えましょう。
はぎの花
おばな くずはな
なでしこの花
おみなえし
また ふじばかま
あさがおの花(ききょう)
思い出すためのキーワード
花の名前をある程度覚えたら、語呂合わせをヒントに、思い出しましょう。
キーワードはこちら。
「おみなえし」「すすき」「ききょう」「なでしこ」「ふじばかま」「くず」「はぎ」
「おみなえし」「ききょう」「なでしこ」「はぎ」「すすき」「くず」「ふじばかま」
旧仮名づかいです。
ハスキーって、ハスキー犬のことではなくて、かすれ声のこと。風邪をひいたときとかの、しゃがれ声もハスキーです。
かすれ声のお袋(お母さん)。でも、ハスキー犬に似たお母さんも…いい。

まとめ
秋の七草は、鑑賞用。
・・・由来は、奈良時代の『万葉集』山上憶良の歌から。それぞれの花は、俳句の秋の季語になっています。
おみなえし、ふじばかま、ききょう
・・・覚え方は「おすきなふくは?」「ハスキーなおふくろ」。
![]()
ススキやクズは、今も空き地に群生していますが、カワラナデシコやキキョウ、フジバカマなど、絶滅が危惧されているものもあります。
お近くの植物園なら、すべての秋の七草に出会える可能性が高いです。
昔から大切にされてきた、日本人の秋を感じたいですね!